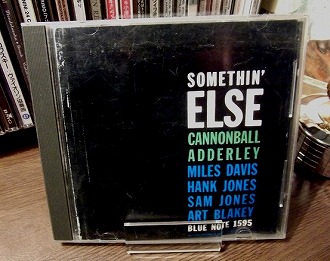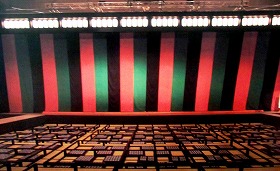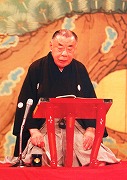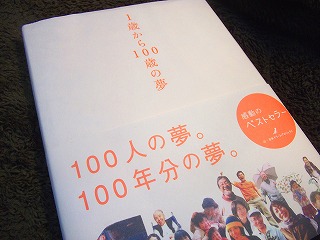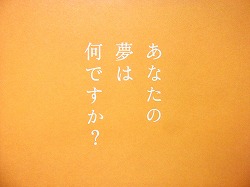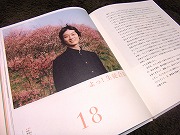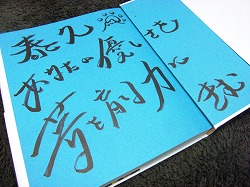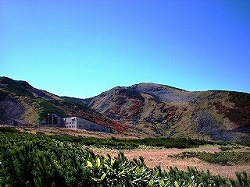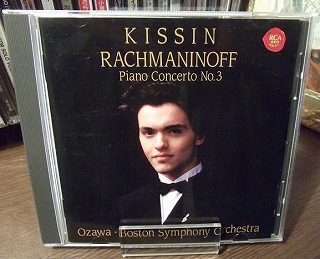美味探究 part18 -薬膳 編-

ここ数日の京都の冷え込みは厳しい。
こう寒い日が続くと、食べるものも
なるべく体を温める効果があるものを
積極的に取り入れたいと思う。
よく使うのが、
生姜、にんにく、そしてごぼう、れんこんなどの根菜類だ。

今回はこれに骨付きの鶏肉を加え

サムゲタン風のスープをつくってみた。
生姜とにんにくを先にオリーブオイルで炒めておく。

それに骨付き鶏と香辛料を加え、じっくりとスープをとる。

使う香辛料の一つが「八角」

これでアジアンテイストな甘い香りがつき
奥深い香りのスープになる。
今回はそれにクミンシード、ローリエを加え、
塩こしょうで味をととのえた後、
いただきものの無農薬のゆずも少し入れた。

体が温まるヘルシー食材満載の一品、
「サムゲタン風スープ」が完成。

また同時に、根菜類をたっぷり使った
「がんもどき風あつあげ」をつくってみた。
材料はこちら。

れんこん、ごぼう、長芋、人参、これら根菜類を
たっぷりと細切りにし、

水切りした豆腐、すりおろした長芋とまぜる。

今回は少し贅沢にアクセントとして
季節の食材、銀杏とホタテも加えてまぜた。

仕上げにごま油、硬さ調整に小麦粉を少々加え、
最後の具材「ごま」を振りいれ準備完了。

あとは低温でじっくりと揚げる。

こちらもヘルシー食材満載の
「がんもどき風あつあげ」完成。

アツアツで、外はサクッと、中はフワフワ。
出来たてならではの美味しさをほおばり、
体も芯まで温まった。