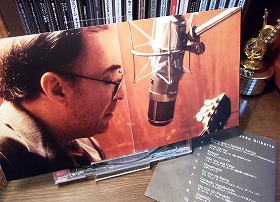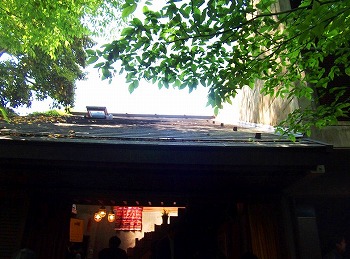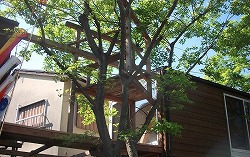空間をつくる -採光計画 編-

室内への光の取り入れ方で住環境の快適性は大きく変化する。
なるべく自然光を室内に取り込む工夫をしながら、
季節によって異なる日射角度を考慮した採光計画が
快適な住宅づくりの重要なポイントになる。
吹抜けにトップライトを設けると、
狭小間口の住宅でも中央部に
より多くの光を取り込むことができる。
逆に窓を床面近くに設けたり
外からの光をグレーチングで
ワンクッション受け止めることで
室内に入る光をやわらかくデザインすることもできる。

最近は室内と外部空間との一体感を持たせるために
フルオープン開口窓の計画も多い。


一方、窓を小さく分割することで
外からの視線を遮りながら
移りゆく光の変化を楽しむことができる。



また欲を言うならば、
窓からの眺めは住む人にとって
心やすらぐ絵画のようでありたい。

通風や家族のコミュニケーションを考えて
つくられた室内窓

部屋から比叡山が望める仕掛けでもある。
室内の心地良さを中心に考える採光計画だが、
夜になると一転、
今度は室内の明かりが外へ放たれる。


住まいが持つ違った表情が現れる。